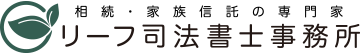税法上の相続財産の範囲とは
相続が発生した場合に、税法と民法では、相続財産の範囲には相違があります。
税法では、「遺贈や相続で継承した財産」、「みなし相続財産」、「相続スタートから3年以内に享受した贈与財産」、「相続時精算課税制度が適用される贈与財産」の4種類を相続財産としています。
今回は、それぞれの相続財産の範囲を詳しくお伝えします。
遺贈や相続で継承した財産
遺贈や相続で継承した財産のうち、金銭で示せるすべての財産は相続財産です。具体的には、現預金や不動産、株式、自動車や貴金属などの動産、特許権や賃借権などの各種権利、売掛金や原材料などの事業用資産などが該当します。
遺贈や相続で継承した相続財産に関しては、2点注意が必要です。
1.名義預金
1つ目は、名義預金が相続財産に含まれる点です。
名義預金とは、名義上のオーナーと実際のオーナーに相違が有る預金のことです。亡くなった方が他人の名義による預金を持っている場合、税法上は亡くなった人の財産とされます。
2.借地権
2つ目は、借地権が相続財産に含まれる点です。
自宅を建設する目的などで他人の土地を借りている権利が相続財産にあり、その権利を相続した場合、たとえ他人の土地であったとしても相続財産となるので注意が必要です。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、相続していないものの税法上は相続しているとみなす財産の総称です。具体的には、死亡退職金や生命保険金、定期金の契約などが該当します。
こうした財産は税法上相続財産ですが、死亡退職金と生命保険金については、取得する全額が相続税の徴税対象となるわけではありません。
徴税対象となるのは、「500万円×法定相続人の数」で求めた金額を上回る部分のみです。一例を挙げると、死亡退職金が2,000万円、法定相続人が2人の場合、1,000万円のみが徴税対象です。
相続スタート前3年以内に享受した贈与財産
相続スタート前から数えて3年以内に享受した贈与財産は、税法上の相続財産です。よって、通常の相続財産と同様に相続税の算出に加算しなくてはいけません。
相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産
相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産が有る場合には、税法上の相続財産に加算する必要があります。
相続時精算課税制度とは、2,500万円を上限に取得した贈与財産について贈与税を無税に出来る仕組みです。無税の金額が大きいものの、贈与を受けた資産について相続税の算出時に加算しなくてはいけません。あくまで徴税の繰り延べであるため、税法上は相続財産に含めるわけです。
まとめ
税法上のルールを確認すると、一般的なイメージでは含めないものも相続財産に含まれます。計算の際に加算し忘れることのないように、かならず税法上の相続財産を確認する必要があるでしょう。