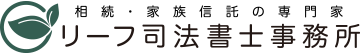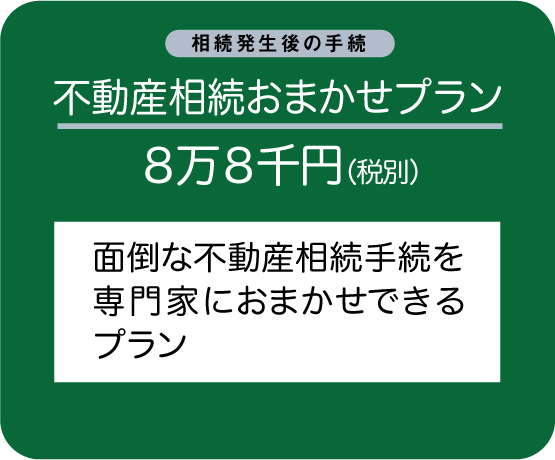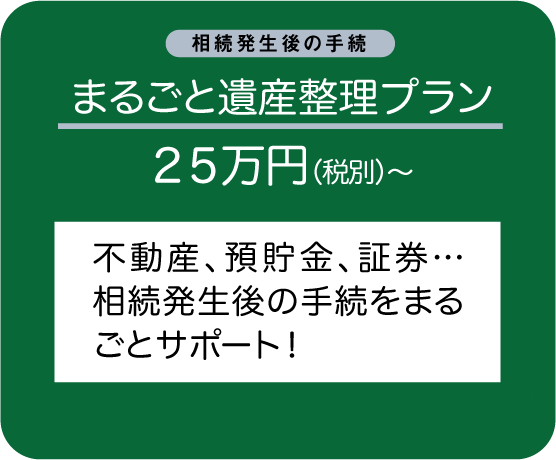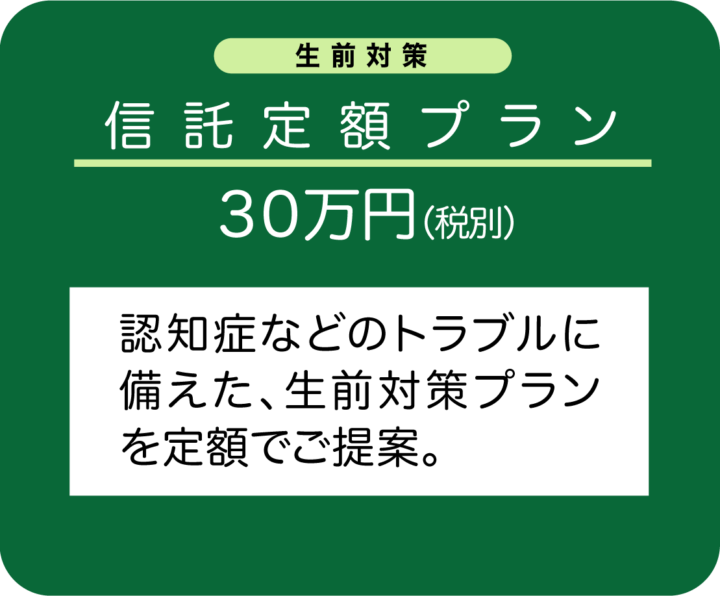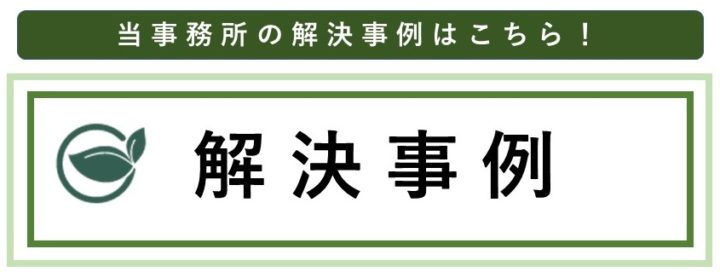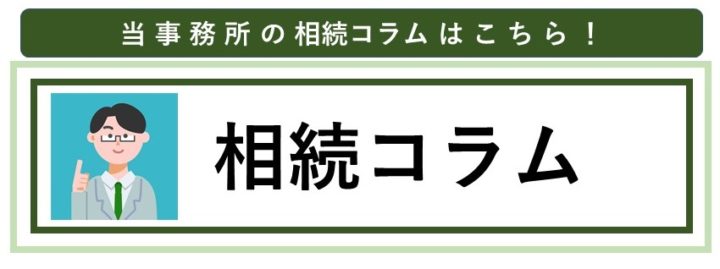【法務局に保管した遺言書】相続発生後の手続とは?|川崎市登戸の司法書士が解説!
遺言書を法務局で保管する制度がまってから、しばらくたちます。
遺言書を法務局へ預けた後、遺言者が亡くなったら、どのような手続が必要なのでしょうか?
こちらでは、遺言書を法務局に保管した方の、相続が発生した後の手続について解説します。
遺言書を法務局へ保管した後の相続手続
遺言書による相続手続を行うには、「遺言書」が必要となります。しかし、法務局に遺言書の原本を預けているので、手元に遺言書がありません。
よって、法務局に遺言書の情報を証明する書類を請求する必要があるのです。
遺言の内容を実現させるためには、「遺言書情報証明書」が必要
遺言書情報証明書とは?
遺言書情報証明書とは、遺言書の内容の情報を証明する書類です。この書類は遺言書が預けられている法務局に請求することで取得することができます。
「遺言書情報証明書」を請求できる人
主には次の人が請求できます。
| 1 | 相続人 |
|---|---|
| 2 | 受遺者 |
| 3 | ①と②の親権者や後見人等の法定代理人 |
| 4 | 遺言執行者 |
法務局における遺言書の保管等に関する法律については、法務局における遺言書の保管等に関する法律を参照ください。
「遺言書情報証明書」を取得するために必要となる資料
請求する際の必要な書類は、次のとおりです。
| 1 | 交付請求書 |
|---|---|
| 2 | 戸籍一式(亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍) |
| 3 | ③ 請求する人の住民票 |
必要な戸籍は誰が相続人になるかで、異なります。
よって、こちらでは原則的に必要な戸籍謄本をあげております。
請求方法について
請求方法は、必要な書類を全てそろえて、法務局へ請求をします。
請求方法は、郵送と直接法務局で受け取る方法があります。
直接受け取る場合は事前に予約する必要があります。
まとめ
法務局に遺言書を保管していると、相続手続きの際に「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。請求できる人は、相続人、受遺者、その法定代理人、遺言執行者です。
必要な書類は交付請求書、戸籍一式、請求者の住民票です。
よって、相続手続を行う順番としては、次のとおりとなります。
| 1 | 戸籍の収集 |
| 2 | 遺言書情報証明書の取得請求 |
| 3 | 不動産や預貯金の相続手続 |
以上となります。
相続手続は、ご家族の状況に応じて必要なお手続きが異なります。
ご不明な点などがあれば、専門家に相談することをオススメします。